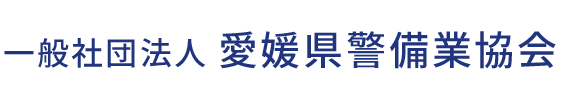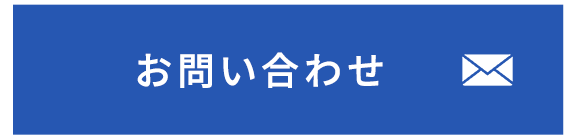警備業
警備業
警備業の概要
日常生活のあらゆる場面で、警備業は人々の生命・身体・財産を守っています。
適正な警備業務を行うために、警備業者には警備業法で、厳しい条件が課せられています。
警備業者の認定制度
警備員の制限
警備業務の基本原則
護身用具等
また、服装についても制限があります。
検定合格警備員の配置基準
書面の交付義務
警備員教育等
警備業の種類
1号業務 施設警備(施設の安全を確保する)
事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等の施設において盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務出入管理、巡回、監視等の業務を通じて、異常の有無の確認、不審者や不審物の発見、警察機関等への連絡、初期消火等を行います。
最近では、テロの警戒を受ける空港施設、港湾施設、原子力施設などのいわゆる重要施設における警備や、子供の安全を確保するための学校警備など、施設警備の警備対象施設は多岐にわたっています。
1.施設警備業務
ビル、工場等の施設に警備員が常駐し、出入管理業務や巡回業務を行います。
また、ビル、工場等の施設に各種のセンサーを設置し、その施設内で侵入者や火災等の異常を監視するいわゆる「ローカルシステム」の施設警備業務のひとつです。
2.巡回警備業務
警備員はビル、工場等の施設に常駐せずに、複数の警備業務対象施設を車両等で巡回します。
3.保安警備業務
デパート、スーパー等大規模店舗の店内を警備員が巡回し、万引き等の店内犯罪を警戒し、防止します。
4.空港保安警備業務
航空機のハイジャック等を防止するため、機器等で旅客等の手荷物や所持品を検査します。
5.機械警備業務
ビル、工場等に各種センサーを設置し、「警備業務対象施設」とは別の基地局で侵入者や火災等の異常を監視し、センサー異常を感知した場合には、警備員が現場に駆けつけます。このうち、住宅を対象としたものが、いわゆる「ホームセキュリティ」と呼ばれています。
機械警備業務は、夜間無人化するビル等で多く行われており、巡回警備業務と併用して行う場合もあります。近年、時短や休日の増加、治安情勢の悪化、セキュリティ機器の高度化等を背景として、急速に機械警備の需要が拡大しています。特に、ホームセキュリティの普及、ATM機のコンビニへの設置、学校警備の必要性等が機械警備の浸透に拍車をかけています。
2号業務 雑踏警備(イベントや交通の安全を確保する)
人や車両が雑踏する場所、またはこれらの通行が危険な場所において、負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
1.交通誘導警備業務
道路工事現場、駐車場等において、交通渋滞や事故の発生を未然に防止するために、警備員が車両や歩行者の誘導を行います。この交通誘導警備業務は、わが国特有の業務といわれています。
2.雑踏警備業務
祭礼、イベントなどで不特定多数の者が参集した場合、群集心理が働き、思わぬ事故が発生することがあります。参集者の安全を守るため複数の警備員が警備部隊を編成し、雑踏の整理、誘導を行います。
3号業務 運搬警備(貴重品や核燃料物質等危険物の運搬時のあんぜんを確保する)
運搬中の現金、貴金属、美術品、核燃料物質等危険物の盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
1.貴重品運搬警備業務
現金、手形、小切手等有価証券、貴金属等の運搬警備業務に加え、最近はユーザー店舗内に設置された入金機を利用した売上金回収業務の需要が増えています。
また、ATMへの現金カセットの装填、回収だけでなく、機械警備業務を連動してATM管理業務トータルに行うなど、取り扱う業内容は年々拡大しています。
2.核燃料物質等危険物運搬警備業務
核燃料サイクルを展開する原子力発電所など各原子力関連施設間における運搬警備業務です。
最近の国際テロの脅威から、核燃料物質等危険物運搬時の安全確保対策が強く求められています。
4号業務 身辺警備(人の生命・身体の安全を確保する)
人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
一般的に「ボディガード」と呼ばれているものです。
治安情勢の悪化と、安全に対する社会気運の高まりに伴い、身辺警備のニーズは、政財界の要人、芸能人、スポーツ選手、一般市民、子供にいたるまで広範囲に及んでいます。
最近は、GPSを利用した「位置情報サービス」や一般女性や子供といった犯罪弱者を対象にした「エスコートサービス」の需要が高まっています。
警備業の教育制度
常に高品質の警備業務を提供するために、警備員の知識、能力の向上に努めています。
警備員の法定教育制度
| 新任教育制度 | 現任教育制度 | ||
|---|---|---|---|
| 新たに警備員に従事する警備員は、新任教育を受けてから警備業務に就きます。 警備員として最低限習得するべき基本教育(基礎的法令や知識、心構え、技能等)を学び、さらに業務別教育を受けた後、それぞれの現場において実地に教育を受けます。 |
現任の警備員は、年度ごとに現任教育を受けます。 現任の基本教育及び業務別教育は、各業務、現場の実態に即した教育を実施し、警備員の知識及び能力の維持向上を図っています。 |
||
| 基本教育時間 | 20時間 |
基本教育時間 | 10時間 |
| 業務別教育時間 | 業務別教育時間 | ||
警備員指導教育責任者制度
警備業を営むためには、営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者を専任させる必要があります。専任の警備員指導教育責任者は、警備員に対する指導及び教育を行うとともに、警備員の配置に関して警備業者に助言を行います。
また、専任の警備員指導教育責任者は、定期的に「現任警備員指導教育責任者講習」を受講し、絶えず専門的な知識及び能力の向上を図っています。
警備員指導教育責任者の資格を得るためには、都道府県公安委員会が実施する警備業務の区分に応じた「警備員指導教育責任者講習」の修了考査に合格する必要があります。
この警備員指導教育責任者制度は、教育を主軸とした警備業の基盤確立とレベルアップに大きく機能しています。
検定資格者配置
特定の種別の警備業務を行うときは、種別に応じ合格証明書の交付を受けている警備員を配置して、警備業務を実施させなければなりません。
| 種別 | 警備員 | 配置人数 |
|---|---|---|
| 空港保安警備業務 | 空港保安警備業務に係る1級検定合格警備員 | 空港保安警備業務を行う場所ごとに1人 |
| 空港保安警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 | エックス線透視装置が設置される場所ごとに1人以上 | |
| 施設警備業務 (防護対象特定核燃料物質取扱施設に限る) |
施設警備業務に係る1級検定合格警備員 | 施設警備業務を行う敷地ごとに1人 |
| 施設警備業務係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 | 施設警備を行う敷地内の防護対象特定核燃料物質取扱施設ごとに1人以上 | |
| 施設警備業務 (空港に係るものに限る) |
施設警備業務に係る1級検定合格警備員 | 施設警備業務を行う空港ごとに1人 |
| 施設警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 | 施設警備業務を行う空港の敷地内の旅客ターミナル施設又は当該施設以外の当該空港の部分ごとに1人以上 | |
| 交通誘導警備業務 (高速道路又は自動車 専用道路に限る) |
交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 | 交通誘導警備を行う場所ごとに1人以上 |
| 交通誘導警備業務 (都道府県公安委員会が認定した路線) |
交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 | 交通誘導警備を行う場所ごとに1人以上 |
| 核燃料物質等危険物 運搬警備業務 (防護対象特定核燃料物質等に係るものに限る) |
核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級検定合格警備員 | 防護対象特定核燃料を運搬する車両又は伴走車その他の運搬に同行する車両のいずれかに1人 |
| 核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 | 防護対象特定核燃料物質運搬車両(上記の車両を除く)ごとに1人以上 | |
| 貴重品運搬警備業務 (現金に係るものに限る) |
貴重品運搬警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 | 現金を運搬する車両ごとに1人以上 |
| 雑踏警備業務 | 雑踏警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員 | 雑踏警備を行う場所ごと(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び状況その他の事情により当該雑踏警備業務実施の適正の確保上当該場所が2以上の区域に区分される場合は、その区分ごと)に1人以上 |
| 雑踏警備業務に係る1級検定合格警備員 平成22年6月1日から施行 |
上記に加え雑踏警備を行う場所(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当該雑踏警備業務実施の適正の確保上、当該場所が2以上の区域に区分される場合に限る)ごとに、1人 |
- 合格警備員とは、各種別の合格証明書の交付を受けている警備員
- 愛媛県公安委員会が認定した路線はこちら(施行日:令和3年4月1日)
上記の警備業務を行う場合、当該警備業務の検定合格警備員は、合格証明書を携帯しています。
警備員検定制度
都道府県公安委員会が行う警備員又は警備員になろうとする者についてその知識及び能力に関する検定で、学科試験及び実技試験によって判定されます。
検定の種別及び内容
現在、次の種別について、それぞれ1級及び2級の検定があります。
| 検定の種別 | 内容 |
|---|---|
| 空港保安警備業務に関する検定 | 空港等施設において航空機の強奪等の事故の発生を警戒し、防止する業務(航空機に持ち込まれる物件の検査に係るものに限る。)を実施するために必要な知識及び能力 |
| 施設警備業務に関する検定 | 施設警備業務(機械警備業務及び空港保安警備業務を除く)のうち、警備業務対象施設の破壊等の事故の発生を警戒し、防止する業務を実施するために必要な知識及び能力 |
| 雑踏警備業務に関する検定 | 人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(雑踏の整理に係るものに限る。)を実施するために必要な知識及び能力 |
| 交通誘導警備業務に関する検定 | 工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷者等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係るものに限る。)を実施するために必要な知識及び能力 |
| 核燃料物質等危険物運搬警備業務に関する検定 | 運搬中の核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故の防止を警戒し、防止する業務を実施するために必要な知識及び能力 |
| 貴重品運搬警備業務に関する検定 | 運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務を実施するために必要な知識及び能力 |
登録講習機関制度
検定資格は都道府県公安委員会が実施する直接検定または登録講習機関が行う講習会を修了することによって取得することができます。
「登録講習機関」とは、国家公安委員会の登録をうけた講習機関であり、警備員特別講習事業センター等が登録されています。
登録講習機関が行う講習会を受講し修了考査に合格した場合には、講習会修了証明書が交付され、検定の学科試験及び実技試験が免除されます。講習会修了証明書の有効期間は交付から1年間です。